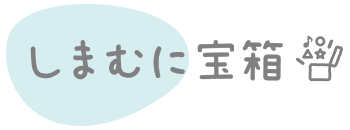これまでの連載では、奄美・沖縄の諸語が危機言語であること、言語が復活した世界の事例、沖永良部島の言語再活性化の取り組みについて紹介した。 今回は、若者たちが〝クールでかっこいいもの〟として伝統言語を捉え直し、今まさに言語復興の時を謳歌しているイギリス、マン島の言語(Manx Language)の事例を紹介したい。
イギリスのマン島(Isle of Man)は、リバプールから3時間ほどに位置する、自治権を持ったイギリス王室属領である。 マン島では6世紀~19世紀半ばまで、ケルト語派のマン島語(Manx)が主要な言語として話されてきた。 しかし、20世紀に入ると、イギリス本島からの移民の増加、強制的な英語教育、島外との接触の増加などによって、マン島語は衰退し、英語へと取って代わっていった。
1899年にマン島語協会(Yn Cheshaght Ghailckagh)が設立されるも、当初は住民の言語再活性化に対する機運も低く、成功を収めることはできなかった。 1974年に、最後の母語話者であるネッド・マドレルが亡くなり、言語は完全に途絶えるかに思われた。 しかし、統計調査によると、1991年に643人だった話者が、2001年の調査では1689人に増加している。 しかも増加分の半数以上が、20歳以下の若者なのだ。 若者たちは、英語の他に、マン島語も流暢に操る「ニュースピーカー(New Speaker)」である。では、なぜマン島語の再活性化が軌道に乗ったのだろうか?
ジョン・マーハ教授は、経済・文化的な背景が大きく影響しているという。 1970年代、2度のオイルショックによって、中東の石油産業から多くの人がイギリスに帰還、その一部はマン島にも流れ込んだ。 イギリス本島からの移住者の増加により、島の伝統が見直され、言語も「守るべき島独自の文化」の一つとして意識されるようになった。 一方で、海外で生まれ育ち、典型的な「イギリス人」ではない移住者自身も、島の文化を自分たちの新しいアイデンティティーと捉えた。 そこにU2やエンヤなど、アイルランド出身の音楽家たちの活躍、ケルト語文化ブームが重なる。 こうした流れの中で、島独自の言語(※マン島語もケルト系である)が、イギリス本国とは異なる「新しくクールなもの」として捉え直されていったのである。
もちろん、地道な研究の蓄積と、地域活動、そして行政の支援が大きなバックアップとなった。 1960年代~70年代にかけて言語学者たちは多くの録音資料を残し、1990年代に数人がマン島語の保育園を始めた。 今では地元政府の後援のもと、マン島語の公立小学校(Bunscoill Ghaelgagh)もあり、70人ほどがここで学んでいる。 保護者たちはマン島語の話者ではなく、教師も後天的にマン島語を学んだ人たちである。 しかし、子供たちは自由にマン島語を操る。島を歩けば、マン島語の標識や店の看板が目に入る。 これが、他地域との違いを際立たせ、観光業にも良い影響を与えている。

小学校でマン島語を学ぶ子供たち "A day in the life of the Bunscoill Ghaelgagh"
マン島語の事例には、考えさせられる皮肉もある。それは、この復興が「母語話者がいなくなってから本格的に始まった」ことである。 マン島語の復興運動が始まったころ、母語話者の中には 「若者たちにマン島語が分かるわけがない」「若者たちのマン島語は間違っている」「そんなことをしても昔には戻らない」と、 活動を阻害する人たちもいた。しかし、若者たちが目指していたのは、昔に戻ることではなく「新しいマン島を作ること」であり、 マン島語の母語話者(ネイティブ・スピーカー)になることではなく、不完全でも良いから「マン島語を話せるようになること」であった。
危機言語の復興というと、昔の生活や考え方への回帰と捉えられることも多い。 しかし、伝統を継承したうえで、新しい文化を打ち立てていくことも可能である。 マン島語の事例は、伝統の重みと大切さを思いながらも、新たな息吹を感じる事例である。